職員同士が対談形式で『わたしたちの社会教育』を語ります。
今年度は、職員研修の際に各職員が何に取り組む1年にするか年度目標を語った中から、手掛け、育てている事業の話をします。
職員として、様々な環境、状況の中、悩みや葛藤を抱えながら、その意義や価値、成果を期待し、目標に進むありのままをお伝えし、社会教育施設の存在意義についても考えていきます。
また、社会教育協会理事の荒井文昭先生(前・東京都立大学人文社会学部人間社会学科教授)にも同席していただき、荒井先生の視点から講評をいただきます。
第5回の今号は、子育て支援カフェモグモグ(日野市から受託運営)の職員・粟澤稚富美に、日野市立みなみだいら児童館(日野市から受託運営)の職員・林実梨が話を聞きます。
(写真 左:林/中央:粟澤/右:荒井文昭さん)
『こどもの声を聴くこと』とは。
林
粟澤さんが仕事をするうえで、「こどもの声を聴くこと」は、いつも大切にしていることですか?
粟澤
センターで企画しているスタディーツアーで、幸福度の高いといわれる国、デンマークを訪れたのですが、私がなぜ行ってみたいと思ったかの話にもつながります。
日本でも、こどもの声を聴いていないわけじゃないし、誰もがこどもの幸せを願っているのに、何が違うんだろう?どうして差が出るんだろう?という問いのヒントをもらおうと思いました。
行ってみてわかったことは、こどもたちが自分で選ぶことができて、選ぶことが幸せに近付くのではないか、ということでした。差があるとすれば、日本では普段から「決める」ことに慣れていないのかなと感じます。
子育て中のお母さんと話す中で、今日の1日の予定をチャットGPTに聞いて決めるという話を聞きます。
こどもの年齢や、起きた時間、ご飯を食べた量や、今日の天気を入力し、今日どうやって過ごしたらいい?と聞くと、例えば今日は雨が降っているから、午前中は屋内のプールに行きましょう、午後は体が疲れているので、ゆっくり過ごして、夕方また元気になるから、夕方からはまた体を動かす施設に行くと、夜もぐっすり眠れますよ、みたいに、言われたとおりに行動しているらしいのです。
決めてもらうことが安心で、自分で決めることに自信がないのだな、と感じます。
林
初めての子育てのときは、考える材料もない、みたいなところもありますよね。
粟澤
こどものことを一生懸命考えているからこそなんですよね。夜中に何度も起きてぐっすり眠れないんだったら、どうしたらぐっすり眠れるんだろうと工夫するし、ご飯もいっぱい食べてもらいたいし、そのために助けてもらっているんですよね。
遊びの場面でもこどもが自分で決めていないと感じることはあります。こどものときの「食べる」「寝る」以外の主体的なことは「遊び」しかないのに、周りの子との関わりの中で、たとえばおもちゃの取り合い一つとっても、自分が遊びたくて近寄ったおもちゃを他の子が遊んでいたら、大人がこどもを抱っこして場を離してしまう場面を見ます。これって、その子の「あれが良かった」「遊びたかった」という気持ちを無視していることになりますよね。
林
おもちゃの取り合い場面、トラブルになる前に制御しちゃう大人が多いですよね。
粟澤
それは増えたと感じます。コロナ禍も影響しているかもしれません。人との関わりを怖がるというか、トラブルにならないように予防しているような。自分の気持ちを言えたり、わかってもらう経験をする機会が減っていることにつながります。
声を聴くことって、その子のやりたいと思うことを後ろから見守ってあげることもひとつなのだと思います。そういうことができている子は選べるようになるし、失敗したって別になんとかなるさって思える子になるのかなと思います。
自分はこれがやりたかった、使いたかった、取られて嫌だった、そうした色々な気持ちを表現していい、その気持ち自体が悪いことじゃないから、と。いやだった、悲しかった、泣きたかった気持ちに蓋をしないで、泣いた自分も認めてもらえる経験を積んで、そうだったんだねって見守ってあげる姿勢が大人に必要なのかな、と。
こどもは自分の気持ちは我慢して、順番やルールを守って、けんかしないように、という風に大人がそういう場面ばかりを作ってしまうと、こどもが自分の気持ちに気付く機会を奪ってしまっているのではないかと思います。
林
こどもが初めて他者との関わりが持てて、自分以外の子の気持ちにふれる機会なのに、取り合いやけんかになる前に、離されちゃうと、他の子との関わりが生まれないですね。こどもの頃から、その子をまるごと認めてあげて、こどもの気持ちを尊重できると、自信を持てるようになるのでしょうか。
粟澤
その子自身が気持ちや、自分の意見を言うことが当たり前になるんじゃないかなと思います。知らないままだと、大人がこういうことを願ってるだろうなと察して発言する子ばかりになっちゃうんじゃないかな。こどもの頃から、出来ても出来なくても、自分は自分でいいんだって気持ちがないと、自分で決めることにいつまでも自信が持てないままになっちゃうのかな。
林
一方で、こどもの声を聴きすぎて、こどもの自由奔放やわがままにつながっているように見えて、大人もこどもの意見を聴かなければいけないという考えばかりが先行していて、大人の立場が弱いように感じることもあります。
粟澤
私も「声を聴くってなんだろう?」と思うとき、例えばどんなに小さい子にも、写真撮ってもいい?と訊くようにしていて、少しずつ大きくなっていく中で、そういえば訊かれていたなっていう経験をその子が積むことで、誰かに訊かれなかった時があったら、なんでこの人は訊いてくれないの?と、「あれ?」と気付くきっかけになると思います。
だから、願いを聴いて、わがまま放題を聴いているわけではなく、いつも訊かれていれば大切にされていることを実感するのではないかなと思います。こどもの声を聴くって、大切にされていることを伝えるメッセージだと思うんですよね。
- こどもと関わる現場の職員、左から林、粟澤
社会的マルトリートメント・こどもにとっての社会は?
粟澤
大人が良かれと思って整備してきていることは、大人が便利なもので社会を作ってきていて、こどもの声が入っていないのではないか?こどもにとってはどうなんだろうという、価値観の見直しが必要なんじゃないかという考えがあります。大人の「良かれ」が不適切な関わりになるのではないか、という考えです。
昨年、「社会的マルトリートメント」という言葉を知りました。まず、マルトリートメントとは「おとなのこどもへの不適切な関わり」を意味する言葉で、虐待の4つの分野(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)を含む概念で、具体的に起きていることを指し示します。
このマルトリートメントが社会の中で当たり前になり、見過ごされてしまう状況に対して「社会的マルトリートメント」という言葉を用いて問題提起する団体があります。(注)
また、こどもの人権や健康を侵害するという視点で、こどもが育つ環境において社会全体が不適切な関わりにつながることを防ごうと全国でアクションが起こっています。
林
社会的マルトリートメントの予防というのが、そういう大人の考え方を考え直すっていうことなのでしょうか。
粟澤
大人の価値観、物差しを見直そう、と言っています。例えば日本のこどもの睡眠時間が世界一短いと言われていますが、こどもが遅い時間まで勉強していることが当たり前になっていることが、こどもの育ちを考えたときにどうなんだろうという視点です。
林
難しいけど、単純になくせばいいという問題じゃない気がします。社会全体で考え直そうという動きがこれから広がっていくのでしょうか。
粟澤
体罰禁止法が出来て、5年程(まだ、びっくりするほど新しい)が経ち、やっちゃいけないということが当たり前になってきました。このように何年も何十年もかけ、変化、浸透していくのかなと思います。
林
こども家庭庁ができて、世の中の動きも変わっていくのでしょうか。
粟澤
こども家庭庁の「はじめの100か月の育ちビジョン」がすごくいいなと思っています。保護者、養育者のウェルビーイングの向上や、『こどもは安心と挑戦の循環で育つ』などのビジョンが書いてあります。
その安心と挑戦の循環ってすごく大事だなと思っていて、親はずっと近くにいてくれると安心だけど、そうすると、挑戦して行く機会がないし、挑戦の時は、親はついて行かないで、戻って来る場所になって、安心を作ってあげていたら、こどもはそれを繰り返していけるんだよということが、私は多くの保護者の方に知ってもらいたいなと思っています。
林
小さいときからできれば、その子たちが大人になったときに、こどもの声を聴くことができるようになるということですね。
粟澤
デンマークの小学校では、多様なこどもが集まる共同体の中で、相手を尊重して話を進めることを体験する場が学校だ、という話を聞きました。こどもだけじゃなく、大人にとっても安心できる社会を、周りの人と作っていきたいなと思います。
林
目指していかないと実現しないですもんね!
粟澤
何かが出来る、出来ないという価値観ではなく、幸せだと感じることが大事で、こどもも大人も若者も、みんな自分を好きになってもらいたいです!
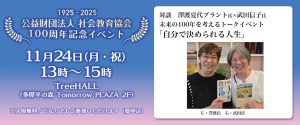
ここで紹介した団体、子どもたちの育つ環境の課題に気づき、改善に取り組む『一般社団法人ジェイス』の代表理事である武田信子さんは、来たる2025年11月、トークイベントにご登壇くださいます。
荒井先生からの講評
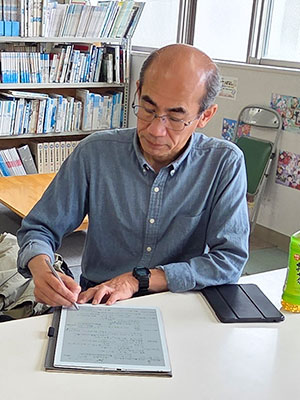
おもちゃの取り合い場面で子どもたちのトラブルになりそうになると、大人が察知して制御してしまうことが多い。このやりとりが印象的でした。自分の気持ちをがまんして、ルールを守る場面ばかりをつくっていると、子どもが自分の気持ちに気づく機会を奪ってしまうとともに、自分に自信が持ちにくくなってしまうことになる。自分以外の子の気持ちにふれる機会が減ってしまうという二人のやりとりに、わたしもその通りだなぁと思いました。声を聴きすぎると子どもがわがままになってしまうという不安が大人にあることに対して粟澤さんは、子どもの声を日常から聞くということは、わがまま放題を聞いているわけではない。気持ちや意見を聞くことが、「大切にされている」ことを子どもに伝えるメッセージになると、応答されていたことも印象的でした。
子どもの意見表明権とは、無視されることを拒否し、関係をまわりに求める権利なのだということを、わたし自身あらためて考えることができました。


