職員同士が対談形式で『わたしたちの社会教育』を語ります。
昨年から始まり、第4回となる企画。今年度は、職員研修の際に各職員が何に取り組む1年にするか年度目標を語った中から、手掛け、育てている事業の話をします。
職員として、様々な環境、状況の中、悩みや葛藤を抱えながら、その意義や価値、成果を期待し、目標に進むありのままをお伝えし、社会教育施設の存在意義についても考えていきます。
また、社会教育協会理事の荒井文昭先生(東京都立大学人文社会学部人間社会学科教授)にも同席していただき、荒井先生の視点から講評をいただきます。
第4回テーマは『児童館でのこども会議の運営』です。
ひの社会教育センターが日野市から受託運営している、日野市立みなみだいら児童館の職員の林実梨に、ひの社会教育センター副館長・山本江里子が「こども会議」話を聞きます。
(写真 左:林/中央:山本)
こども会議とは…
こども家庭庁のこども基本法に基づいた、こども・若者の意見を政策に反映させるための取り組みのひとつで、「こども会議」の実施に関するガイドラインも策定されている。
山本
ではさっそくですが、こども会議って、どんなことをするんですか?
林
こども家庭庁からのガイドラインで、児童館での取り組みとして「こども会議」の実施について策定されていますが、やり方の形は定まっていないので、試行錯誤中です。
山本
これまでやってきたのは、どんな方法・内容でしたか?
林
昨年度は、各学期に一度、実施しました。今年度は、月に一度行うことにして、毎月5~6回『遊びタイム』という時間があり、毎月15日に、翌月の『遊びタイム』の遊び内容を決めるというやり方で取り組み始めました。
※『遊びタイム』は、体育室で集まり、一つの遊びに参加して、みんなで遊ぼうという時間。提示する遊びに参加することで、集団遊びの経験や、きっかけを出して参加を促しています。
お便りや貼り紙で会議があることをお知らせして、当日いる子たちに声を掛けて集め、実施。今年度、毎月15日と決めたことと、「こども会議」という名前の硬さを感じていたので、「ぷらねっとミーティング」に変えたことで、浸透してくれるといいな、と思っています。
山本
会議のテーマを決めることが大変そうですね。
林
昨年度は、児童館でやりたいことを聞いたり、年度末には、ちょうど児童館についてのアンケートを取った時だったので、「困っていること」について共有しました。館内で危険だと思うことについて、解決方法を話題にしたら、意見が色々出てきました。
山本
そういう場面では6年生がとりまとめている?
林
学年はバラバラで、高学年がまとめる雰囲気でもなく、みんなから意見が出ます。
体育室での遊び方についての提案で、自分に関係のあることだったので、ヒントがあれば考えられることや、当事者意識が大事だなと思いました。
山本
こども会議で、大人の立場として何か気を付けていることはありますか?
林
否定せず、どんな意見も最後まで聞くことです。
山本
子どもたち同士もそれはできている?
林
ルールとして最初にみんなに伝えています。人の意見をちゃんと聞くこと、「ダメな意見」はないこと、みんなのことを考えた意見を言うこと、というルール。
児童館のこととか、他の子たちのことも考えられるといいねっていうことは言っています。
児童館には普段からポストがあって、書いて出す方が言いやすいこともあり、意見を自由に入れられる準備はしています。
こども会議に、まずは慣れてもらって、子どもたちがそういう場なんだ、発言していい場なんだってわかっていくと、きっともっと面白くなるんだろうなと思います。
こどもの声を聴くこと
山本
林さんが子どものとき、そういう場にいた経験はありますか?
林
私は児童館にはあまり行っていなかったのですが、学校で先生には気持ちや意見を言えていた方かなと思います。今は言えない子たちの方が多いのかな。
みなみだいら児童館でも、いつでも意見を言ってきていいよって、ポストもそうですけど事務室の扉を開けています。本当は「会議」というよりも、よっぽど普段の方が子どもたちの意見を直接聞けていると思います。
山本
現場レベルでは「子どもの声を聴く」ことは、日常のコミュニケーションの中で取り組んでいるというところで、会議という形でやる意義を、疑問に感じられているのは、わかる気もします。
林
児童館にはこども会議よりずっと前から『子ども実行委員会』があり、児童館でのイベントの時に、企画・準備などを中心になってやってくれます。
子どもたちの意見から生まれて、やりたいっていう子が意識的に来てくれるという意味では、すごくこども会議に近い、むしろ同じと言ってもいいぐらいの役割は果たしているんじゃないかなと思います。
学校ではなかなかみんなの前に立てない子が、そういうところでスポットライトを浴びることができるという意味ですごくいいなと思います。
山本
日本人って会議が苦手と言われますが、子どものころから経験を積み重ねると楽になると思いますか?
林
それもやる意味の1つだと思っています。ただ、勇気を出して言った自分の意見が、何かの形になったとき、それを子どもたちにフィードバックして、反映されたんだという、繰り返しが大事だと思います。
こども会議をやる上で、フィードバックまでやることが重要と、研修でもよくいわれています。
その過程を経て子どもたちの自主的主体性が育つのかな、と。
一方、そこまで形にするのが大変だという現実の壁にぶち当たります。他児童館なども悩みは同じようです。
山本
同じ悩みを抱えている、他の児童館さんと情報交換をされている中で、成功例やいいヒントなども得られていますか?
林
市内の児童館で、子どもたちとそうした場を持つことがうまいと言われている館長さんがいらして。求心力があり、子どもたちへの言葉掛けなど、真似したくなるテクニックがあるらしく、見て学びたいと思っています。市内児童館の10館合同の研修で話を聞きたいくらいです。
でもそれは、普段からの関係性があるからこそできることだなと思っていて、わざわざ集めて、「会議」と名のつくものを設定しなくても…、という葛藤がまた生まれます。
山本
今までのお話を聞いて感じたのは、林さん自身も迷いの中にあって、こども会議って素敵!と思える段階にまだ入っていないのかな。
林
うーん、でも完成はないとは思うんですよね。正解とか完成はないだろうなと思います。自分の中でビジョンがそのうち固まってくるとは思っています。
山本
子どもたち同士、生活や遊びの中、対立や衝突の手前で、対話を始める、知恵を学ぶことの必要性が問われているのかもしれません。
子どもたちも、そういうやり方があるんだって分かってくると、会議の積み重ねで、いい効果になっていくのかなと思います。子どもたちが「回避」の意味を知っていくことは、大きな意味があると思います。
林
実際は、「本音を聞く」のは、「表」の会じゃなく、2人で遊んでいるときや、オセロをやっている時間とか、そういう「裏」の場面でポロっと出てくるんですよね。だから、日常的に大事にして、その子たちが意見を言える、自信になれるように積み重ねていきたいと思います
山本
今「裏」って言ったけど、きっと会議の捉え方が、「表」はこうあるべきって、私たちも知らないうちに感じてしまっていて、裏も表もないよって、自分の意見は表だからこそ出さなきゃダメっていうことを子どもたちにも伝えていかないといけないですね。と同時に対立じゃなく対話だよということを、私たち大人も改めて学びたいなと思います
林
大人が始めから無理だと諦めてしまうようなことでも、子どもたちはユニークな視点で意見を出してくれます。その意見が、「もしかしたら、工夫次第でできるかも?」と、私たち大人のやる気を引き出してくれることがあります。やっぱり子どもたちの純粋な意見は素敵だし、いいなって思います。
山本
こんな会議、こんなテーマでやってみたいというのはありますか?
林
今はこちらで決めているキャンプの行き場所やプログラムとか、子どもたちと1から決めるのも楽しいだろうなとか、児童館の看板が古くなってしまったので、みんなで作るとか、みんなとやりたいなと今思い描いています。何かを作るためのゴールのある会議ばかりイメージしがちですが、これについて語ろうみたいな、哲学的な答えの出ない会議も設けたいと思っています。例えば社会的な問題や、なんで勉強しなきゃいけない?などの永遠の疑問、子どもたちにそうした問いを投げかけたら考えると思います。意見が違っても、みんな合ってるんだって思える、そういう機会があると、ちょっと学校に行きたくない子とか、救われる子もいるんじゃないかなと。
反面、児童館には子どもたちは遊びに来てるということが大前提で、会議をやる時間だから集まって!というのは、遊ぶ時間を奪ってまで必要なことかな、という難しさがあります。こちらが意図的に変えてしまうのは違うかな、と。
山本
まだまだ試行錯誤と迷いの中にいる様子ですが、今後の展望はありますか?
林
形だけ整えようとするのは簡単なこと。今は児童館内でも私一人で担当していますが、誰でも関わって、誰でも出来る仕組みづくりをみんなで勉強したいと思います。
荒井先生からの講評
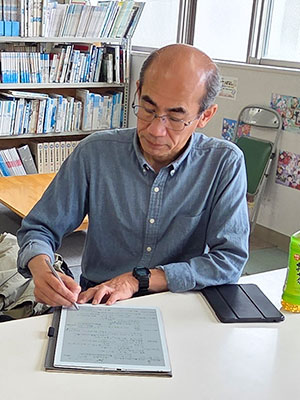
【荒井先生からの講評】
子どもが意見を表明することを、基本的人権として保障していく。そのための実践と理論の構築が、求められています。けれども、子どもが保護される対象であると同時に権利の主体であることを理解し、実践することは、大人側にとって簡単なことではありません。子どもたちが児童館に「遊び」に来ているのは、どうしてなのでしょう。子どもたちも大人と同じように「追われて」生活していることが話題になりました。児童館のなかではホッとできたり、友だちとおしゃべりしたり、遊んだり、ケンカをしたりすることができる。これらのことが「楽しい」とは、どういうことなのでしょうか。児童館ですごす時間と空間は、子どもたちからすれば家庭や学校空間の映し鏡として存在しています。子どもの声をじっくりと聞いてあげること、そして職員側からの声かけによって、子どもたちは自分を取り戻していく基盤をつくっているのではないでしょうか。話を聞かせていただいて、そんなことを考えました。

